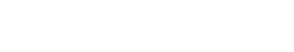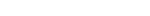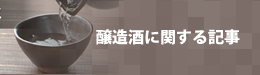【ウイスキー】ジャパニーズ・ウイスキーについて
概要
今、世界中のウィスキーファンから注目されているウィスキー、それが「ジャパニーズウィスキー」です。
スコッチウィスキーなどに比べると歴史的には浅いですが、その品質の高さには以前から定評がありました。
といってもジャパニーズ・ウィスキーの誕生の瞬間から人気があった訳ではなく、何回かの浮き沈みを経て現在のジャパニーズ・ウィスキーブームを迎えています。
以下に、ジャパニーズ・ウィスキーの歴史や背景などについて見ていきたいと思います。
ジャパニーズ・ウィスキーの歴史について
ジャパニーズ・ウィスキーの始まりと言うと、サントリー創設者の鳥井信治郎さんとニッカ創業者の竹鶴政孝さんを思い浮かべる人も多いのではないかと思います。
本格的なジャパニーズ・ウィスキーの造りのキーマンとして、この二人の名前が挙げられることに異論を挟む人はいないと思いますが、
実際のジャパニーズ・ウィスキーの始まりは、更に歴史を遡ることになります。
また、サントリー・ニッカといった大手以外でも、古くから地ウィスキーを作り続けている酒造所もありますが、ここではジャパニーズ・ウィスキーの歴史に深く関わっているこれらの2社を中心に以下触れていきたいと思います。
(ジャパニーズ・ウィスキーの黎明期)
具体的には江戸時代の鎖国政策時、長崎の出島に出入りしていたオランダ商人を通して、日本人は西洋のウィスキーの存在を知っていたとも言われています。
はっきりと文献に記されているウィスキーとして一番歴史が古いのは、1854年にアメリカのペリー提督が日米通商条約を締結させるために黒船で日本を訪れたときです。
この際、ペリー提督は将軍への手土産として、アメリカ産のウィスキーとその他の洋酒を持ち込んだと記録に残っています。
もともと日本では古くから「焼酎」という蒸留酒が作られていて、西洋式の蒸留酒であるウィスキーに対しての抵抗感も低かったのかもしれません。
こういった貢ぎ物のウィスキーを味わって、日本でも西洋式の蒸留酒ウィスキーを実験的に作り始めましたが、当時は果汁や香料、スパイスなどが加えられていたと伝わっています。
そういう意味では、現代の定義でいう「ウィスキー」ではなく、「リキュール」に近いものだったと想像できます。
そして1873年、アメリカやヨーロッパ諸国を視察して回った「岩倉使節団」が日本に帰国し、その際にスコッチウィスキーや西洋の各種の蒸留酒を持ち帰ったことで、日本に本格的な西洋式の蒸留酒「ウィスキー」が定着するきっかけとなったと言われています。
記録によれば、明治天皇にも献上されたのだとか・・・
(ちなみに、このとき使節団が持ち帰ったスコッチウィスキーは、「オールド・パー」だったそうです。)
(ジャパニーズ・ウィスキーの創世期)
1899年にはサントリーの創業者、鳥井信治郎さんが「鳥井商店」を興して、ぶどう酒の製造・販売を始めます。
その後名前は「壽屋洋酒店」に改称、やがて後の「サントリー」へと繋がっていきます。ここで発売された「赤玉ポートワイン」が大ヒットし、鳥井さんは巨額の富を得ます。
そしてその資金を元手に、長年の夢であった「日本人の繊細な舌に合うジャパニーズ・ウィスキー造り」へと邁進していきます。
鳥井さんが目指したのは、着色料などを混ぜた、当時の日本の「イミテーション・ウィスキー」ではなく、ウィスキーの本場スコッチ・ウィスキーにも負けないような本格的なウィスキー造りでした。
時を同じくして、ニッカの創業者である竹鶴政孝さんは、実家が広島の造り酒屋(現在でも「竹鶴酒造」として日本酒を作っています)だったこともあり、大阪工業高等学校(現在の大阪大学)の醸造科で酒造りの勉学に励みます。
竹鶴政孝さんは、当時新しい存在であった洋酒にも興味を持ち、卒業を待たずして洋酒製造で有名だった「摂津酒造(現在の「宝酒造」)」に入社します。
このときに竹鶴さんが頼ったのが、高校の先輩で摂津酒造の常務であった「岩井喜一郎」さんで、岩井さんは本坊酒造へのウィスキー造りの指導を行なった人物としても知られています。
そして1918年、摂津酒造では純国産の本格的ウィスキー造りに参入することを計画、竹鶴さんを単身スコットランドに派遣します。竹鶴さんはグラスゴー大学で有機化学と応用化学を学びつつ、積極的に現地のウィスキー蒸留所を見学して回ります。
更には蒸留所頼み込んでウィスキー造りの実習(研修)をさせてもらうこともあり、実際には「ロングモーン蒸留所」(スペイサイド地方、エルギン地区)と、「ヘーゼルバーン蒸留所」(キャンベルタウン地方)で現地修行を行なったと言われています。
つまりジャパニーズ・ウィスキーの誕生の背景にはスコッチ・ウィスキーがあり、ジャパニーズ・ウィスキーの英語表記がスコッチ同様、「Whisky」であるのもこれに由来すると言われています。
竹鶴さんは、1920年にはスコットランドで知り合った女性リタさんと国際結婚をして、同年11月にはリタ夫人を連れて日本に帰国します(このあたりのいきさつは、NHKの連続ドラマ「マッサン」でも描かれていましたね)。
そして竹鶴さんの研修の集大成である報告書、通称「竹鶴ノート」を岩井さんに提出し、いよいよ摂津酒造での本格的なウィスキー造りが始まります。
しかしながらこの時期、不運なことに第一次世界大戦後に起こった世界恐慌により、資金不足により摂津酒造ではウィスキー造りを断念せざるを得ない状況に追い込まれ、竹鶴さんも1922年には同社を退職します。
そして翌1923年、いよいよ本格的なウィスキー造りに着手しようとしていた壽屋の社長、鳥井信治郎さんはスコットランドからウィスキー造りの技師を招聘しようとして、現地に適任者の有無を問い合わせます。
そこで得た回答が「わざわざ技師を呼び寄せなくても、日本には竹鶴政孝という適任者がいるはずだ」でした。
こういった縁もあり、竹鶴さんは同年6月に寿屋に入社します。
1924年には京都の山崎で「山崎蒸留所」が竣工して、竹鶴政孝さんはその初代所長になります。
1929年、紆余曲折を経てようやく会社が自信を持って国産ウィスキーだと胸を張れるウィスキー「白札」が出荷されます。
しかしながらイミテーションウィスキーに慣れてしまった日本人の舌には「白札」は受け入れられず、ビジネス的な成功を収めるまで
には、1937年発売の「角瓶」まで待たなければなりませんでした。
一方で、鳥井さんと竹鶴さんの蒸留所に対する考え方の違いも浮き彫りになりました。
竹鶴さんが「スコットランドに近い風土の北海道で蒸留所を作るべきだ」との考えに対し、鳥井さんは「輸送コストや工場見学などの際の利便性を考えると大阪近郊が理想だ」との考えでした。
そして竹鶴さんが入社してから10年がたった1934年、竹鶴さんは自身が理想とする北海道余市町で蒸留所を作るべく、寿屋を退社します。
竹鶴さんは1934年の7月に北海道余市に「大日本果汁株式会社」を設立します。
この会社の略称の「日果」が、後の「ニッカウヰスキー」へと繋がる訳ですね。ウィスキーを商品として販売し、利益を得るには何年もの歳月がかかります。
そこで竹鶴さんは、地元の特産品であるリンゴを使ってリンゴジュースを作り、その利益を貯めてウィスキー造りの資金に充てる算段でした。
従ってこの「大日本果汁株式会社」という名前は、当時としては「名は体を表す」意味でもピッタリくるネーミングだったということですね。
やがて1940年、余市で製造された最初のウィスキーが販売され、1952年には社名を改称、「ニッカウヰスキー」と命名されます。
(ジャパニーズ・ウィスキーの混乱期)
戦前・戦中・戦後の時期は、ウィスキー業界に限らず日本全体が極度の混乱期でした。
しかしながらジャパニーズ・ウィスキーに限って言えば、日本全国で極度の貧困や飢えで苦しんでいたにも関わらず、ウィスキーには軍事上の特権が与えられていました。
つまり帝国海軍の御用達としてウィスキーが採用され、配給用の統制品としてウィスキーは製造されることになります。
さらに戦後の占領下においても、アメリカの占領軍がウィスキーの消費を下支えしていくことになります。
何とも皮肉な歴史の因果ではありますが、こうしてジャパニーズ・ウィスキーは戦争を乗り越えて作られていくことになります。
(ジャパニーズ・ウィスキーの発展期)
1950年代に入り、徐々に戦争からの復興が見え始め、同時に日本の経済力も強まってくると、サラリーマンを中心に洋酒が受け入れられていきます。
戦争直後は深刻な物資不足から粗悪なカストリ※などのお酒が出回りましたが、終戦後の1946年、サントリーは早くも「トリス」ブランドでウィスキーを販売し始めます。
この「トリス」は、戦火を免れた山崎モルトをキーモルトとして、サントリーがこれまで培ってきたブレンド技術を駆使して造られた国産ウィスキーです。
サントリーはこれを「トリスバー」という業態で売り出し、トリスのハイボールが爆発的にヒットして日本で初めてのウィスキーブームを
巻き起こしました。
東京ではこれを「トリハイ」、大阪では「Tハイ」と呼び、当時の「二級酒」という位置づけの庶民性も相まって、トリスは日本人に受け入れられていきました。
※「カストリ」の詳細については、焼酎のページをご参照ください。
さらにジャパニーズ・ウィスキーが日本人に浸透してくると、今度は様々なランクのウィスキーが発売されるようになってきます。
サラリーマンの給料の多寡によって、飲むウィスキーのランクが変わってくるというのものです。
一番有名なサントリーのブランドで紹介しますと、上述した「トリス」は「庶民のお酒」の代表的なものですので、まずはここからスタートする人が多かったそうです。
やがて少しずつ昇格していき、給料が増えていくにつれて飲む銘柄は、「角瓶」→「オールド」→「リザーブ」→「ローヤル」と変わっていったのだとか・・・。
「出世魚」ならぬ「出世酒」ということですね(笑)。
(ジャパニーズ・ウィスキーの低迷期)
こうして広く日本人に親しまれてきたジャパニーズ・ウィスキーですが、やがて「冬の時代」に突入していきます。
1985年前後をピークとして、ウィスキーの消費量は下降していき、かわってワインやカクテルなどのお酒が好んで飲まれるようになっていきます。
その理由は定かではありませんが、一つのきっかけとなった出来事が1989年4月の酒税法改正であったと言われています。
この改正によりウィスキーの級別制度は廃止され、結果として従来の2級・1級のウィスキーは大幅値上げを余儀なくされ、ウィスキーの消費低迷はさらに加速されます。
加えてこの酒税法改正で国産ウィスキーと輸入ウィスキーの税率差も解消されました。
これは当時のイギリスの首相、「鉄の女」と呼ばれた、「マーガレット・サッチャー」さんの強力な圧力によるもので、「サッチャー・ショック」とも言われています。
(ちなみにこのサッチャーさんですが、好きなスコッチは、「グレン・ファークラス」だと巷間伝わりますが、真偽の程は不明です。)
また1990年代に入り、日本人のお酒の嗜好はさらに多様化します。
ワインやカクテルに加えて地ビール(クラフトビール)の台頭や本格焼酎ブームなど、ますます消費者の注目は国産ウィスキーから離れていきます。
さらに追い打ちを掛けるように1997年、今度はEUから日本の酒税格差について下記のようなクレームがつけられます。
曰く「ウィスキーやブランデーは焼酎やリキュール類に比べて税率が高く、これは貿易障壁にあたる」と。
これを受けて日本は再度酒税法を改正せざるを得なくなり、結果的に焼酎やリキュール類の税率を引き上げ、逆にウィスキーやブランデーの税率は引き下げられました。
これは何を意味するのでしょうか。
確かに、ウィスキーやブランデーが好きな人からすれば、これらの酒類の税率引き下げはウェルカムなことで、従来よりも安価で入手が可能になりました。
一方で、上述した「出世酒」のように、ウィスキーが高価であったことのステータス感は薄れていくことになり、「海外旅行でのお土産」や「贈答品」としての「憧れのウィスキー」という地位は、失われてゆくことになっていきました。
(ジャパニーズ・ウィスキーの黄金期)
上記のように1980年代後半以降、長く冬の時代が続いたジャパニーズ・ウィスキーの業界ですが、徐々に以下のような変化の兆しが現れ出します。
1つは1990年代に入ってから起こったスコッチ・ウィスキー、中でも「シングル・モルトウィスキー」ブームの広がりです。
それまではごく一部のマニアの間でしか知られていなかったようなスコッチが、日本に続々と輸入されるようになり、それを飲んでさらに
奥の深いモルトウィスキーの世界に目覚めるウィスキーファンが増えていきました。
これは上記のように、酒税法の改正がプラスに働いたことの一つであると思います。
スコッチのモルトウィスキーの素晴らしさに触れたウィスキーファンが、スコッチにも比肩しうるジャパニーズ・ウィスキーの存在に気づき始めたということですね。
2つめは2000年代に入ってから相次いだ、ジャパニーズ・ウィスキーの世界的な品評会での受賞ラッシュです。
「山崎」「白州」「響」「余市」などなど・・・。
これらのお酒の特定のエイジ※のものが最高金賞を受賞する事態が毎年のように発生し、それだけでなく大手メーカー以外の小さい作り手のウィスキーも多くのメダルを受賞するようになりました。
こうなると世界のウィスキーファンも「スコッチの二番煎じ」とは言えなくなり、ジャパニーズ・ウィスキーを無視できない状況になりました。
とは言っても海外のバイヤーがジャパニーズ・ウィスキーを買い漁るようになるのは、もう少し先の話になります。
※「エイジ」については別途後述します。
そして3つめが、2000年代後半から急拡大した「センベロ酒場→千円でベロベロに酔っ払える酒場」で盛んに飲まれるようになった、「ハイボール※ブーム」の影響です。
ウィスキーが冬の時代を迎える前にも、空前の「ハイボールブーム」はありました。
補足ですが、ジャパニーズ・ウィスキーをベースにしなければハイボールと呼べない訳ではありません。
スコッチで作っても、バーボンをベースにしても、ウィスキーのソーダ割りは全て「ハイボール」になります。
念のため申し添えておきます・・・。
しかしながらそのブームの担い手の多くはサラリーマンであり、ほとんどは男性が中心でした。
その意味では今回は「第二次ハイボールブーム」と言えますが、第一次ハイボールブームとの大きな違いは、サラリーマンだけでなく若い学生や女性までもが争うようにハイボールを飲むようになっている点です。
前述したように、2000年以前のハイボールのイメージは「中年のオヤジがくだを巻きながら飲むお酒」でした。
それが今ではすっかり老若男女に浸透し、その原料となるジャパニーズ・ウィスキー※の消費も急拡大していきました。
※「ハイボール」の名前の由来等の詳細については、スコッチのページをご参照ください。
その理由についてですが、いくつかの要因は考えられるものの、上述した竹鶴政孝さんの半生を描いたテレビドラマ、「マッサン」の放映が2014年に始まったことも、ジャパニーズ・ウィスキーブームに拍車を掛けた一因であったと言われています。
このような状況は現在(2020年2月現在)でも続いていて、ハイボールブームがヒートアップするあまり、深刻な原酒不足に陥ったり、ジャパニーズ・ウィスキーブームが過熱しすぎて驚くほどの高値で取引される銘柄が出てきたりと、ブームの影の部分も目立ってきています。(このあたりは改めて後述します。)
タイトルには「黄金期」と書きましたが、すでに現在では黄金期を過ぎてジャパニーズ・ウィスキーの「転換期」に入っているのかもしれませんね。
ジャパニーズ・ウィスキー(モルト)ができるまで
ジャパニーズ・ウィスキー(モルトウィスキー)の製法については、もともとがスコッチをお手本にしていることもあり、基本的にスコッチ同様の造り方です。
従って詳細はスコッチウィスキーのページをご参照いただければと思いますが、以下には主にジャパニーズ・ウィスキーとスコッチウィスキーとの製法の差がある点を中心に述べていきたいと思います。
①製麦(モルティング)
大麦には、二条大麦と六条大麦の2種類がありますが、ウィスキーを作る際に使われるのはデンプンの含有量の多い二条大麦です。
この点はスコッチウィスキーと同様ですが、ジャパニーズ・ウィスキーの原料となる大麦のほとんどは、海外からの輸入品です。
今、日本各地で造られているクラフト蒸留所の中には、この大麦も地元産のものを使おうという動きもあります。
二条大麦から麦芽を作る作業を「製麦」といいます。
さて、大麦に含まれるデンプンですが、これはこのままではアルコール発酵する訳ではないので、まずはデンプンを糖化する必要があります。
これは他の穀物類を原料とするお酒造りと同様です。
このため、大麦を温水に浸して(浸麦)、まず発芽させます(この際に使用される浸麦槽を「スティープ」と言います)。
十分に水を吸収した二条大麦を床に広げて、適度な温度・湿度下の環境に置くことで、発芽が進行してデンプンを糖分に変えるさまざまな酵素が生成されてきます。
注1.酵素の生成が十分な量に達した段階で、発芽の進行を止めます。
発酵には酵素が必要ですが、発芽が進みすぎると今度は酵素が消費されることになります。
従って、適度な発芽の状態で発芽の進行を止めます。
発芽の進行を止めるには、大麦を乾燥させて水分を取り除く必要があり、この作業を行うところが「キルン」と呼ばれる麦芽乾燥塔です。
ここで、ピート※や無煙炭を焚いて、熱により麦芽を乾燥させて発芽の進行を止めます。
スコットランドの燃料として一般的なピートですが、日本では北海道の湿原や一部の地域でしか採取されず、ピートを焚いて発芽の進行を止めている日本の蒸留所のほとんどは、ピートを輸入しています。
しかしながら、「真の国産ウィスキーを造る」という強い信念を持つクラフト蒸留所も存在し、実際に国産のピートを使っているところもあります。
※ピート(泥炭)の詳細については、スコッチのページをご参照ください。
注1.「フロアモルティング」
水分を吸収した麦芽を床に広げる作業ですが、伝統的なやり方では、発芽が均一に進むように、木製のシャベルのような道具(シール)を
使って絶えず攪拌を繰り返します。
これを「フロアモルティング」といいますが、重労働でもあるためこれを行う蒸留所は地元スコットランドでもほとんどなくなりました。
今では、「モルトスター」と呼ばれる専門の麦芽製造業者から原料を仕入れている蒸留所が一般的です。
日本でも「イチローズモルト」で有名な秩父蒸留所では、わざわざ「モルトスター」にまで出向いてこの「フロアモルティング」経験し、
実際にこうして製麦された原料を使ってウィスキーを仕込んでいるそうです。
最後に、麦芽にとって不要な根っこを機械で取り除いて、原料となる麦芽の完成です。
②糖化(マッシング)
乾燥が終了した麦芽は、細かいゴミや小石などを取り除いた上で、「モルトミル」という機械で粉砕されます(粉砕された麦芽のことを「グリスト」と言います)。
この「グリスト」ですが全て均一という訳ではなく、概ね3種類の粉砕に分かれます。
一番粗い「ハスク(粗挽き)」、一番細かい「フラワー(細挽き)」、その中間の「グリッツ(中挽き)」です。
一般的な配分として「ハスク」が15~20%、「グリッツ」が70~80%、「フラワー」が5~10%程度になるように調整され
ます。
これは、糖化工程の最後に麦汁を濾過する際、「ハスク」が多すぎるときれいに濾過ができず、逆に「フラワー」が多すぎると濾過層が目詰まりを起こしてしまうため、これらの事態を防ぐよう上記のような比率となっています。
この「グリスト」を、「マッシュタン」と呼ばれる金属製の器(糖化槽、仕込槽)に移し替えます。
このマッシュタンに約70度のお湯を加えて、ゆっくりと混ぜ合せます。こうすることで、麦芽の酵素がデンプン質を糖分に変えて、甘い麦のジュースのような麦汁を作り出します。
次に、こうしてできた麦汁を濾過して糖化液を得ます。
この糖化液(糖液)を「ウォート」あるいは「ワート」と呼びます。
この濾過に際しては、麦芽が沈殿することで自然にできた濾過層を利用して、麦汁が濾過されます。
これら、麦芽をお湯に溶いて糖分を得る工程(あるいは糖化液そのもののこと)を「マッシュ(マッシング)」と言います。
③発酵(ファーメンテーション)
「ウォート」は冷却され、「ウオッシュバック」と呼ばれる巨大な発酵タンク(桶)に移されます。
ここで酵母(イースト菌)※が加えられ、アルコール発酵が始まります。
ウオッシュバックには、伝統的な木製の桶とステンレス製のものがあります。
木製の発酵槽(ウオッシュバック)は優れた保湿性があり、木に棲み着く乳酸菌が液体に独特の風味をもたらすと言われています。
一方、ステンレス製タンクは清掃が容易で発酵の安定性が高く、品質の管理がしやすいという利点があります。
※イースト菌(酵母)
酵母は、ウィスキーの香味を形作る重要なポイントになっていて、ウィスキー専用の複数の種類の酵母を組み合わせて使われます。
どのような酵母を使用するのかは各蒸留所ごとの秘密となっていますが、ウィスキー用の酵母は数種類と言われています。
これに対して日本酒用の酵母は、100種類以上あるとも言われています。
アルコール発酵が始まると、酵母の働きにより「ウォート」に含まれる糖分は、アルコールと二酸化炭素(炭酸ガス)に分解されます。
ウィスキーにおいては、発酵温度が30度以上と他の酒類に比べて高いため、発酵期間は2日から3日間と、比較的短い期間でアルコール発酵を終了します。
こうして得られた醪(醸造酒)は、アルコール度数6%から8%程度で、この醪のことを「ウオッシュ」あるいは「ディスティラーズ・ビア」と呼びます。
できあがった「ウオッシュ」は度数もビールに似ていますが、殺菌処理をしていない状況下で作られる点がビールと異なります。
これはウオッシュに含まれるバクテリアが、この後の「蒸留」の過程で重要な役割を果たすからです。
従来、スコットランドの蒸留所ではあまりこの「発酵」の過程に重きを置いていませんでしたが、近年ではビール業界を参考にして、様々な注意を払って「発酵」に取り組むようになっています。
④蒸留(ディスティレーション)
発酵が終了した醪(ウオッシュ)は、蒸留機(釜)に送られて蒸留が始まります。
あらためての説明になりますが、「蒸溜」とはアルコール濃度を濃縮し、アルコール度数を高めるための工程です。
スコッチのモルトウィスキーの製造に使われるのは、「ポットスチル※」と呼ばれる銅製の単式蒸留器(釜)です。
日本がお手本としたウィスキーがスコッチですので、伝統的な日本の蒸留所ではスコッチ同様、「ポットスチルを使って2回蒸留」を守っているところも多いです。
その一方で、ジャパニーズ・ウィスキーには酒税法以外に明確なウィスキーの定義がなく、近年では最新の「ハイブリッド型蒸溜器」※を導入している蒸留所も増えてきました。
※「ポットスチル」の詳細については、「お酒基本」及び「スコッチ」のページをご参照ください。
※「ハイブリッド型蒸溜器」
単式蒸留器と連続式蒸留機が一体となった蒸留器です。
ハイブリッド型蒸溜器の一番の特徴は、ポットスチルの横に「精留塔」と呼ばれる銅製の円筒がついているところです。
「精留塔」の中は複数段の棚に分かれていて、この段(棚)を1回通すとポットスチルで1回蒸留したのと同じ効果を得られます。
「半連続式蒸留器」※の最新版と考えると分かりやすいかもしれないですね。
この蒸留器の便利な点は、品質面や効率面に優れているだけでなく、ウィスキーとジンなどの複数種類の蒸留酒を一つの蒸留器で使い回すことができるという点です。
「お酒の二毛作」が可能になり、それだけにビジネスリスクを回避させることにつながります。
小さい蒸留所などでは今後導入が広がっていくかもしれませんね。
※「半連続式蒸留器」の詳細については、「ブランデー」のページをご参照ください。
伝統的なウィスキーの製法を守っている蒸留所のほとんどは、2回蒸留を行います。
1回目の蒸留は「ウオッシュスチル(初留釜)」で、2回目の蒸留はやや小さめの「スピリットスチル(再留釜)」(「ローワインズスチル」とも呼ばれます)で行います。
多くの蒸留所で、初留と再留で別々のポットスチルを使用しています。
ポットスチルの加熱方式には大きく2通りのやり方があります。
1つは石炭やガスで直接ポットスチルを熱する「直火焚き方式(直火式)」で、伝統的なやり方です。
もう1つは、ポットスチルの中にパイプを通して、蒸気で加熱する「スチーム式(間接式)」です。
直火焚き方式に比べると、焦げ付きの心配や清掃の手間も省けることから、現在ではこちらのスチーム式が主流になっています。
また、ポットスチルの形状やサイズもその味わいに大きな影響を与えます。各蒸留所ごとに自分達が目指すウィスキーの味わいを計算し、その設計図に従ってポットスチルも製造されるという訳です。
上記のようにして、ポットスチルで加熱された醪はアルコール成分が気化し、ラインアームを伝って冷却器に運ばれ再び液化します。
こうして得られた液体は、「ローワイン」と呼ばれます。
最初の初留で得られた「ローワイン」のアルコール度数は約20%前後、再留で得られるローワインのアルコール度数は約70%まで跳ね上がります。
こうして無色透明のウィスキーの原酒、「ニューポット」(「ニューメイク」とも呼ばれます。)が誕生します。
1回目の蒸留と2回目の蒸留方法に大きな違いはありませんが、2回目の蒸留の際には、コンデンサー(冷却装置)の下に「スピリッツセイフ」と呼ばれるガラスの箱が置かれ、コンデンサーにより液化されたアルコールがこの箱を通る仕組みになっています。
これは、熟成に回す原酒を見極めるための装置で、流れ出るアルコールの種類は以下の3つに分けられます。
①フォアショッツ(「ヘッド」「前留」とも呼ばれます。)
最初に流れ出るアルコール成分です。
②ミドル(「ハーツ」「ハート」「中留」とも呼ばれます。)
中間で流れ出るアルコール成分です。
③フェインツ(「テール」「後留」とも呼ばれます。)
最後に流れ出るアルコール成分です。
上記の①や③は、アルコール度数が高すぎたり低すぎたり、あるいは不純物が混ざったりしていることがあるため、熟成には回さず、「ローワイン」に混ぜて再度再留釜で蒸留されます。
②の「ミドル」と呼ばれる部分は、最も品質に優れていて、これを取り出して熟成用の原酒にします。
この作業を「ミドルカット」と呼びますが、連続して流れ出る液体のどの部分でカットするのか、熟練の技と経験が要求される作業です。当然のことながらこの作業によっても味わいは大きく異なってきます。
クリアな酒質のウィスキーを求めるならば「ミドル」の部分を更に少量に絞り、逆に個性的で荒々しいウィスキーを目指す場合は敢えて「ヘッド」の部分を入れ込むなど、ここにも蒸留所ごとの性格が現れます。
ちょっと変な例えになるかもしれませんが、日本酒の精米※にも似た作業とも言えますね。
※「精米」の詳細については、「日本酒」のページをご参照ください。
⑤熟成(マチュレーション)
出来上がった「ニューポット」は、いったん貯蔵タンクに入れられます。その後に加水して、アルコール度数を60%前後まで下げた上で、木製の樽に移して熟成に入ります。
これにより無色透明で刺激の強かった液体が、時を経ることで芳醇でまろやかな琥珀色のウィスキーへと変化していきます。
モルトウィスキーの味わいや風味の3/4は、この熟成の工程で決まるとも言われています。
熟成に使われる樽は、ほとんど全てカシやナラなどのオーク材が使われます。
オークは主に2種類で、アメリカ産の「アメリカン・ホワイトオーク」と、ヨーロッパ産の「スパニッシュ・オーク(ヨーロピアン・コモンオーク)」や「セシルオーク」などです。
アメリカン・ホワイトオークは、主としてバーボンの熟成に使われ、スパニッシュオークはシェリー酒やブランデーの熟成に使われることが一般的です。
新樽を使うことはあまりなく、ほとんどが以前に他のお酒を貯蔵するために使用されていた樽を再利用しています。
その中でもバーボンウィスキーの熟成に使われていた「バーボンバレル」、シェリー酒※の熟成に用いられていた「シェリー樽」が有名です。
一般的に、シェリー樽で熟成させたお酒はフルーティで甘みが強く、赤みがかったウィスキーになり、バーボン樽で熟成させたお酒はバニラのような香りでやや薄い琥珀色をしたウィスキーになると言われています。
※「シェリー酒」の詳細については、「その他ワイン」のページをご参照ください。
更にジャパニーズ・ウィスキーの個性を際立たせているのが、「ジャパニーズオーク」とも呼ばれる日本固有のオーク、「ミズナラ」です。
「ミズナラ」は多孔質で柔らかく、樽に加工する際には繊細で壊れやすいという欠点もありますが、うまく熟成させればジャパニーズ・ウィスキーに唯一無二の特徴を生み出します。
具体的には、ミズナラの樽で熟成させたジャパニーズ・ウィスキーには、スパイシーでフルーティといった表現にとどまらず、「お香のような風味」が感じられるとも言われます。
いかにも日本的な、エキゾチックでオリエンタルな味わいの表現ですね。
(熟成の効用について)
上述したように、ウィスキーの熟成に使われる樽のほとんどがオーク材です。
これはオーク材がウィスキーの熟成に最も適していることの証左でもあります。
適度な強度がありながらしなやかであるため液漏れが少なく、また多孔質であるため通気性もよく、熟成中のウィスキーに安定して酸素を供給することが可能です。
このようにしてオーク樽の中でウィスキーは熟成されるのですが、熟成の過程で下記のような化学反応が生じます。
1.原酒に色と風味がつく
樽の中の原酒は、外気の温度によって膨張や収縮を繰り返します。膨張した原酒は、樽の木材に入り込み、逆に収縮した際には樽が以前に貯蔵されていたお酒の風味や色を取り込みます。
こうして徐々に原酒に色と風味がついていきます。
2.雑味成分を取り除く
1.とは逆の効用になりますが、ウィスキーにとって好ましくない雑味成分や特定の風味を樽の木材が吸収します。
これにより、より品質の高い原酒になっていきます。
3.味わいの化学反応を起こす
オーク樽とウィスキー原酒(蒸留酒)が触れ合う過程で、複雑で多様な化学反応を起こします。
これにより、本来のウィスキーの原料である大麦からは想像も出来ない様々な香りやフレーバー(果実、花、ナッツ類やチョコレート、スパイスなど)がウィスキーに加わります。
ウィスキーが「魔法の水」とも呼ばれる所以がここにあります。
4.酸化を起こす
3.の化学反応の1つでもありますが、熟成過程の最後半に近いタイミングで起こるものが「酸化」です。
上述したように、樽に入り込んだ空気とウィスキーが触れ合うことでポジティブな化学反応も起こしますが、一定以上の期間が過ぎると「酸化」が生じます。
これはウィスキーにとってはどちらかといえば「オフフレーバー」※となることが多く、ネガティブな化学反応の1つです。
※「オフフレーバー」の詳細については、「お酒基本」のページをご参照ください。
(熟成に影響を与える要素について)
繰り返しになる部分もありますが、あらためて熟成に影響を及ぼす様々な要素について以下に見ていきたいと思います。
・使われる樽材の種類
上述したように、熟成に最も適している木材はオークですが、そのオークにも様々な種類があります。
さらに日本には、日本固有のオークである「ミズナラ」も存在します。また、樽材の内側を焦がす※のか焦がさないのかによっても味わいは変わってきます。
蒸留所が自分たちの作りたいウィスキーを思い描きながら、それに相応しい樽材をチョイスしていきます。
※樽の内側を焦がす作業を「チャー」と言います。詳細については、「スコッチ」のページをご参照ください。
・使われる樽に何が入れられていたか
これも前述しましたが、一般的に熟成に用いられる樽としては、「バーボンバレル」「シェリー樽」などが有名です。
しかしながら近年では、様々なお酒を熟成させた樽を実験的に試行する蒸留所も多く、下記のように実に多種多様です。
マディラウッド/ラムカスク/ポートウッド/ワイン樽/ソーテルヌウッド/アイラカスク/オロロソ・シェリー/ペドロヒメネス/梅酒/・・・
上記は一般的な名称だけにとどめましたが、「ワイン」「ラム」と一口に言ってもその個別銘柄は何万種類もあり、何のお酒が入れられていたのか一つとっても、その数は膨大なものになります。
樽が何回、どれくらいの期間熟成に使われていたか当然の話になりますが、熟成に使われた回数が多いほど、また熟成期間が長ければ長いほど、樽に入れられていたお酒の影響を大きく受けることになります。
・樽の大きさ
樽のサイズにもいくつかの種類があり※、樽のサイズが小さいほど液体と木材との接触面積が大きくなり、樽材からの影響を大きく受けることになります。
また小さいサイズの樽に入れて熟成させると、熟成も早く進むと言われています。
※樽のサイズ(種類)の詳細については、「スコッチ」のページをご参照ください。
・外気温について
気温が高ければ高いほど、熟成は早く進みます。
台湾の「カバラン」やインドの「アムルット」など、現在では蒸留技術が進化していて、比較的温暖な地域でもウィスキー造りは可能になっています。
加えて日本には四季があり、寒暖の差が激しいという気候特性があります。
こういった自然環境をいかにしてウィスキーの熟成に反映させるのか、蒸留所の力量が問われます。
・湿度について
空気中に含まれる湿度は、樽の中の原酒のアルコール度数を左右します。湿度が高いと樽材に水分が浸みこみ、原酒のアルコール度数は低くなります。
逆に湿度が低いと樽材は乾燥し、樽の中の原酒のアルコール度数は高い状態のまま熟成されます。
・樽の貯蔵方法(置き方)について
さらに細かい要素として、上記の「温度」や「湿度」は樽の倉庫(保管庫)の場所や置き方によっても変わってきます。
貯蔵庫には大きく分けて2つのタイプがあります。
■ダンネージ式
伝統的な貯蔵庫のタイプです。土の上に直接木製のレールのようなものを敷いて、その上に3段から4段程度樽を積み上げていきます。
これ以上積み上げると、樽の重みで下の樽が耐えきれなくなるので、ほとんどの蒸留所では段数を抑えています。
またダンネージ式の貯蔵庫の床は土であることが多く、土から湿気が放出されるため、より湿度が高くなると言われています。
■ラック式
1950年代から60年代に生れた新しいタイプの貯蔵庫です。スチール製のレールを敷くため重量に強く、ラックに8段から12段程度まで樽を積み上げることが可能です。
床はコンクリートであることが多く、貯蔵庫自体に高さがあることから、床部分と屋根付近の温度差が大きくなります。
ラック式は建設費が高くつくという欠点もありますが、樽の移動が機械でできるというメリットもあります。
(熟成期間について)
上述したように、ジャパニーズ・ウィスキーには法律による定義がなく、最低の熟成年数も定められていません。
しかしながらスコッチ・ウィスキーをお手本にしたこともあり、スコッチに倣って最低3年間の熟成を目安にしている蒸留所が一般的です。
ちなみに、「ニューポット」を樽詰めして、まだほとんど熟成されていない熟成途中のウィスキーのことを「ニューボーン」と呼びます。
・ノンエイジウィスキー
ラベルに熟成年数の表記がないウィスキーのことを「ノンエイジウィスキー」と呼びます。
「ノンヴィンテージ」あるいは「ナス」と呼ばれることもあります。「ナス」とは「NAS」、「NonAgeStatement」の略称です。
例えば「10年」の年数表記があるウィスキーの場合、最低でも10年以上熟成させた原酒のみを使っていることになります。
近年では、ジャパニーズ・ウィスキーの深刻な原酒不足により、ノンエイジウィスキーが急増している状況です。
⑥瓶詰め(ボトリング)
こうして熟成を終えた原酒は、ブレンダーにより味がチェックされて、晴れて世の中にリリースされる訳ですが、シングルカスクウィスキー等の一部のお酒を除いては、その樽そのままの原酒が瓶詰めされることはありません。
同じ熟成年数、同じ樽の材質や大きさで熟成された樽であっても、上述したように熟成倉庫の位置や樽そのものの個性など、同じ味になるとは限りません。
そこで、熟成を終えた樽は、いったん大きなタンクに集められ、味を均一に馴染ませてから瓶詰めされます。
また、原酒の多くは50度から55度程度の度数で、このままでは度数が高すぎるので、加水して度数を整えてから販売されます。
以前、ウィスキーの度数は43度が一般的でしたが、近年では40度のものが多くなってきましたね。
ジャパニーズ・ウィスキーにおいてはアルコール度数の規制がありませんので、40度以下のウィスキーも市販されています。
グレーンウィスキーができるまで
グレーンウィスキーの製造工程はスコッチウィスキーの製法とほとんど同様ですので、割愛させていただきます。
詳細は「スコッチ・ウィスキー」のページをご参照ください。
ジャパニーズ・ウィスキーの特色について
上述したように、ジャパニーズウィスキーの中でもモルトウィスキーについては、製法も似通っている部分が多く、テロワール※による特徴こそあるものの、5大ウィスキーの中でも最もスコッチに似た味わいとなっています。
※「テロワール」については「スティルワイン」のページをご参照ください。
では何を持ってジャパニーズ・ウィスキーを特異たらしめているかというと、それはブレンデッド(ヴァッテッド)ウィスキーの製法に関わる部分になります。
すでに「スコッチ」のページでご説明したように、スコットランドには100を超える蒸留所が存在していて、お互いの蒸留所がその原酒を交換し合うことでスコッチの売上の9割を占めると言われる「ブレンデッドウィスキー」を作っています。
翻って日本のウィスキー造りを見てみると、そもそも蒸留所の数が圧倒的に少ない状況です。
クラフト蒸留所が増えてきているといってもその数は限定的で、スコットランドのそれとは比ぶべくもありません。
しかもスコッチ・ウィスキーとは異なり、メーカー間で原酒のやりとりをするような文化もなく、むしろお互いが「秘密主義」を徹底している面のほうが強いです。
このような状況の中で、ジャパニーズ・ウィスキーがどのようにしてブレンデッド・ウィスキー(あるいはヴァッテッドウィスキー)を作っているのかですが、大きくは2つの方法をとっています。
1つは自社の蒸留所で多種類のウィスキーを作ること、もう1つは外国からウィスキーを輸入してブレンドさせる方法です。
すぐに想像がつくかと思いますが、前者の方法がとれるのはかなり大規模な蒸留設備を備えた会社に限られ、実質的にはサントリーやニッカなどのみです。
後者の方法も、小規模蒸留所だけに限られた製法という訳でもなく、大手のサントリーやニッカなどでもウィスキーを輸入してブレンデッドウィスキーを作っています。
日本のウィスキーメーカーの数が非常に少ないことを考えると、ジャパニーズ・ウィスキーの多岐に渡る味わいは驚異的とも言え、その味わいの幅広さを支えているのが世界でもトップクラスを誇るブレンデッド技術の高さです。
近年、ジャパニーズ・ウィスキーは世界各国のコンテストで最優秀賞を受賞しているのは周知の通りです。
ジャパニーズモルトウィスキーの品質の高さもさることながら、何十種類ものモルトとグレーンウィスキー、そして場合によっては輸入ウィスキーも駆使して作られるブレンデッドウィスキーについても、日本人らしい精妙な技術が結実したウィスキーだと言えます。
まさに「交響楽」を体現したようなウィスキーですね。
ジャパニーズ・ウィスキーの定義について
前述したように、ジャパニーズ・ウィスキーの厳密な定義は存在しないと言っても大袈裟ではありません。
唯一の定義らしきものは「酒税法」の中でウィスキーについて触れられている部分ですが、「発芽させた穀類、水を原料として糖化・発酵させたアルコール含有物を蒸留したお酒」程度のざっくりとした規定しかありません。
これは、ウィスキーというお酒の説明としては間違ってはいませんが、ジャパニーズ・ウィスキーの定義と呼ぶにはあまりにも大まかに過ぎます。
同じ酒類なのになぜこのような温度差があるのかということですが、日本酒などと比べてウィスキーやワインなどは、もともと日本になかった酒類であることが原因の1つであると指摘されています。
世界の5大ウィスキー※の中でも、厳格な定義のないウィスキーはジャパニーズ・ウィスキーのみで、スコッチやフランスワインのような原産地の保護に関する規定もありません。
これはどういうことかと言うと、例えば海外から複数のウィスキー原酒を輸入し、国内でブレンドしたものを「ジャパニーズ・ウィスキー」として販売したとしても、何ら法的な罰則はないということです。
(こうして作られたウィスキーを指して「ヴァリンチ・ウィスキー」※と呼ぶこともあります。)
※「ヴァリンチ・ウィスキー」については「スコッチ」のページをご参照ください。
もちろん、このやり方を全否定するものではなく、上述したようにこうした手法を試行錯誤すること自体、ウィスキーメーカーの大切な役割の1つであることは事実です。
実際、こうした手法で作られたジャパニーズ・ウィスキーの中にも、かなりレベルの高いウィスキーは存在します。
しかしながら、日本で蒸留所を持たずに一切の蒸留を行なっていないウィスキーを、「ジャパニーズ・ウィスキー」と呼んでいいものか、甚だ疑問があります。
名称だけの問題ではなく、海外から複数のウィスキー原酒を輸入してブレンドさせる方法は、誰でも容易にウィスキーを販売することが可能で、ジャパニーズ・ウィスキーのブランド価値を損なうリスクもはらんでいます。
実際、スコッチ・ウィスキーにおいても、法整備がなされる前には同じような事例があったそうです。
現在、世界では空前のジャパニーズ・ウィスキーブームが起きています。
実際、世界的なウィスキーアワードで最高金賞を受賞している蒸留所があるのは事実ですが、世間で言うところの「ジャパニーズ・ウィスキー」の中には、上記のように「ブレンド作業のみを日本で行なったウィスキー」も含まれています。
言わば「玉石混淆」の状態が、現在のジャパニーズ・ウィスキーの置かれた現実です。
実は似たような状況は過去にワインの世界でも起きていて、2018年10月に施行された「果実酒等の製法品質表示基準」により、「国産ぶどうを100%使用し、日本国内で製造されたワイン」のみを「日本ワイン」と定義付けました。
(ちなみに海外から輸入したぶどうや濃縮果汁を使って日本で生産されたワインは、「国産ワイン」と呼んでいます。)
同様の動きはウィスキーの業界団体でも起きていて、政府に対してジャパニーズ・ウィスキーの法整備・定義付けの働きかけが現在行なわれています。
1日でも早い法改正の実現が期待されています。
※「世界5大ウィスキー」については、「ウィスキー」のページをご参照ください。
ウィスキーの等級表示などについて
古いウィスキーを見かけたときに、ボトルネックやラベル下部、あるいは裏ラベルなどに「ウィスキー特級」という表示をみつけることがあります。
これは日本独特の酒税法によるもので、諸外国からの強い批判を受けて1989年(平成元年)に級別制度は廃止されました。
従って、ウィスキーのラベルやボトルのどこかに「ウィスキー特級」という表示があるボトルは、1989年以前に瓶詰めされたオールドボトルだということが分かります。
もう少し詳しく酒税法を調べてみると、酒税法の原型は1940年(昭和15年)にまで遡ります。
この酒税法は全てのお酒類に適用されたもので、日本酒にももちろん同様の級別制度※がありました。
※「日本酒の級別制度」については、「日本酒」のページをご参照ください。
その後何度かの改正が繰り返され、1962年(昭和37年)にはそれまで「雑酒」扱いだったウィスキーが「ウィスキー」というカテゴリに区分されました。
従って1962年から1989年までが「ウィスキー特級」という表示があった時代ということになります。
また、表示には特級以外に「一級」「二級」という3つの区分がありました。その区分の詳細については以下の通りです。
・特級アルコール度数43度以上
・一級アルコール度数40度以上43度未満
・二級アルコール度数39度以下
これ以外に「原酒混和率」「原酒増量倍率」などといった指標もあり、それらを総合カテゴリ分けしていたのが正確な実情だったようです。
だだしスコッチなどのウィスキーには混和という概念がないので、ここでは割愛させていただきます。
つまりアルコール度数が高いほど高い税率が適用されたということで、「アルコール度数が高ければ高いほどうまい酒である!」という飲み助の主張?には合致しているような酒税法でしたが、海外からの輸入ウィスキーにはとんでもない関税がかけられていたのも事実です。
例えば一例として挙げられる事が多いスコッチ、「ジョニ黒(ジョニーウォーカー黒ラベル)」ですが、当時をよく知る年配者は「ジョニ黒は高かったな~」などと述懐しがちです。
実際、特級表示が廃止された1989年当時は、「ジョニ黒」は7000円~6000円の価格帯で取引されていましたが、今では2000円台で購入が可能です。
いかに高い関税をかけていたのかが分かりますね。
また当たり前の話ではありますが、この当時の外国産ウィスキーでも海外土産として現地で購入したものには、税関のラベルはついていません。
●税関のアルファベットについて
特級表示と並んで、ラベルにはアルファベットの頭文字と、番号が併記されていることがままあります。
アルファベットは税関の場所を示しているもので、このウィスキーはどこの税関を経由して輸入されたのかが分かります。
例えば以下のようなものです。
・T・・・東京税関
・Y・・・横浜税関
・O・・・大阪税関
・K・・・神戸税関
・N・・・名古屋税関
・OK・・・沖縄税関などなど・・・・
そのウィスキーがどこを経由して日本に渡ってきたのか、そういったことを想像しながら飲むウィスキーもまた格別ですね。
●税関の番号について
税関のラベルは一般的に等級※・アルファベット・番号が併記されています。
※スコッチをはじめとして、この当時の輸入ウィスキーはほぼ全て43度以上あったため、表記は「特級」がほとんどです。
番号はそれぞれの税関で同様にして輸入されたウィスキーにそれぞれ付与されていて、番号が若いほど古い時代に輸入されたウィスキーだということが分かります。
級別制度が廃止される直前には5桁の番号でしたが、もっと以前の輸入ウィスキーには4桁、さらに古いウィスキーには3桁の番号のものもあります。
こうしたところにも注意しながらオールドボトルを探すのも面白いですね。
●容量について
現在では国内・海外を問わずほとんどのウィスキーは700mlがスタンダードです。
ただ過去においては、これよりも容量が多かった時代があり、容量によってもある程度年代の特定が可能になってきます。
例えば「750ml」の容量のボトルは1990年代前半までは流通していました。
さらに容量の大きい「760ml」のボトルは1990年代以前で、ちょうど特級表示があった時代と時を同じくします。
(ジャパニーズ・ウィスキーに特有の容量として、「720ml」のボトルもありました。)
760mlよりも大容量のボトル※があったのかどうかは存じ上げませんが、年々容量が少なくなってきているのは事実のようです。
※スタンダードサイズのボトル容量を指していて、「1L(リッター瓶)」などはこの限りではありません。
●アルコール度数について
アルコール度数については、ジャパニーズ・ウィスキーに限らず全てのウィスキーに共通して近年度数が下がる傾向にあります。
30年程前には43度が主流でしたが、今では40度がほとんどになっています。
テネシー・ウィスキーの代表的な銘柄「ジャック・ダニエル」も、今では40%になっていますがオールドボトルでは43%でした。
ちなみに私は一度だけ「45%」のジャック・ダニエルを見たことがありますが、いつの年代のボトルなのか見当がつきません。
ボトルの容量もそうですが時代を経るにつれてダウンサイジング、アルコール度数は低アルコール化の傾向が強まっています。
ヘビードリンカーにとっては楽しみづらい時代になっているのかもしれませんね。
※「カスク・ストレンクス」については、「スコッチ」のページをご参照ください。
●酒税証紙について
こちらもオールドボトルを特定する際の見極めになるアイテム、「酒税証紙」です。
「酒税証紙」はウィスキーのキャップを覆うように被せられた帯状の紙で、これが貼ってあると「きちんと酒税を払いました」という証拠になりました。
また、開栓してしまうと「酒税証紙」が破れてしまうので、きれいに「酒税証紙」が残っているということは、未開封の証にもなりました。
「酒税証紙制度」は1953年(昭和28年)に制定され、1974年(昭和49年)に廃止されましたので、「酒税証紙」が貼ってあるウィスキーは1974年代以前にボトリングされたものだと推察されます。
・「沖縄用酒税証紙」について
1972年、沖縄が本土に返還されました。1974年の「酒税証紙」廃止前のことでしたので、これを受け日本政府は1972年~1977年まで、沖縄用の「酒税証紙」を発行しました。
沖縄県内の酒屋でも今やほとんど見かけることがなく、マニア垂涎のコレクターアイテムとなっています。もし沖縄旅行にでも行かれる際には、一度探してみてはいかがでしょうか?
●その他のオールドボトルの特定手段
上記のようにオールドボトルを特定する様々な情報があるのですが、それ以外にも下記のような手段があります。
ボトル・ラベルの形状/(スコッチの場合)紋章の違い/バーコードの有無/キャップの相違/本社所在地の表記/マスコットキャラクターの変遷/「従価税」「従価税適用」の表示有無・・・
もちろんある程度の知識が必要ですが、こうした違いが分かってくると、同じ銘柄のウィスキーを年代別の飲み比べるといった楽しみ方も広がります。
奥の深いオールドボトルの世界を味わってください!
・「本社所在地の表記」について
オールドボトルを特定する手段として、上記に「本社所在地の表記」と挙げましたが、これはどういうことでしょうか。
ジャパニーズ・ウィスキーの多くはラベルやボトルネックなどに本社所在地(製造・販売者の住所)が表記されています。
同じ住所であっても長い年月を経る過程で住所の表示が変わるケースがあります。
有名なケースは「サントリー」の住所で、本社の住所は今でも「大阪市北区堂島浜2丁目1-40」です。
しかしながらこの住所は、大阪市の施策の一環で1979年に変更され現在に至っていて、それ以前は「堂島浜通り2丁目」という表記でした。
つまりこの表記のあるボトルは、1979年以前にボトリングされたオールドボトルだと特定され、同じ特級ボトルでも更に古い年代のボトルだということが分かります。
もちろん年代が古くなる分、品質が劣化しているリスクも高まりますが、希少性もさらに高くなります。
こうした違いを認識した上で、オールドボトルを探すのも面白いかもしれませんね。
ジャパニーズ・ウィスキーの様々な蒸留所について
これまでは主に、「サントリー」や「ニッカ」などの大手のジャパニーズ・ウィスキーを中心にジャパニーズ・ウィスキーを紐解いてきましたが、もちろんジャパニーズ・ウィスキーの作り手は2社だけではありません。
昔からこつこつと地ウィスキーを作り続けている蒸留所もあれば、昨今のジャパニーズ・ウィスキーブームの流れに乗って新たな蒸留所を立ち上げたもの、あるいは焼酎や日本酒造りから派生して、新たにウィスキー造りを始めた蒸留所もあります。
特に新世代の小規模生産者の造るウィスキーを指して、「クラフトウィスキー」と呼ぶこともあります。
前述したように、現在のジャパニーズ・ウィスキーを取りまく環境は複雑で、その定義が存在しません。
海外からの輸入ウィスキーを混ぜ合せただけのジャパニーズ・ウィスキーもあれば、自らの蒸留所で作った原酒だけをブレンドして販売しているメーカーもあります。
いわば「玉石混淆」の状態で、実際に自分たちで飲んだ上でそれぞれのウィスキーの品質を見極めることが大事になってきます。
ここでは、主として自前の蒸留所でウィスキーを作っているところを中心に、いくつかの蒸留所を紹介していきたいと思います。
1.秩父蒸留所(埼玉県秩父市)
今ではブームとなっているクラフト蒸留所ですが、その先駆けとなった蒸留所こそがこの「秩父蒸留所」です。
代表の肥土伊知郎(あくといちろう)さんが率いる秩父蒸留所は、「イチローズモルト」として今や全世界に知れ渡っていて、熱狂的なファンも多いです。
代表的なシリーズ「カード・シリーズ」は、トランプの数字とスート(マーク)の組み合わせで54種類(ジョーカーは2枚を加えて)のバリエーションがあり、数字が多くなるほど熟成年数も上がるシステムになっています。
またこのカードシリーズには、すでに廃止蒸留所となってしまった「羽生(はにゅう)蒸留所」の貴重な原酒がブレンドされていることでも知られていて、往年の銘酒を偲ぶことができます。
ちなみに、以前これらカードシリーズの54本一式がオークションに出品され、およそ1億円!!で落札されたことでも話題になりましたね。
ワールド・ウィスキー・アワード(WWA)で3年連続で世界最高賞を受賞するなど、もはやジャパニーズ・ウィスキーを代表する蒸留所と言っても過言ではありません。
2.マルス信州蒸留所(長野県上伊那郡)
本坊酒造が抱える「マルス信州蒸留所」は、地ウィスキーブームの1985年に稼働し、以来30年以上にわたって根強いファンに支えられてきました。
以前はその名の通り、地元での消費が中心でしたが、近年のジャパニーズ・ウィスキーのブームもあって今では日本を代表するウィスキーとなっています。
特に2013年のWWA(ワールド・ウィスキー・アワード)で最高賞を受賞した「マルス・モルテージ3プラス2528年」をきっかけに一気に知名度がブレイク、世界でも「マルス」の名前が広がるようになりました。
また、ジャパニーズ・ウィスキーの創世期にも活躍した、岩井喜一郎さん※が関わった蒸留所としても知られていて、その名前を冠したウィスキーも販売されています。
さらに2016年からは、本坊酒造の発祥地である鹿児島県津貫(南さつま市)で第2蒸留所(マルス津貫蒸留所)が稼働を始めていて、これからも注目の蒸留所です。
※「岩井喜一郎」さんについては、「ジャパニーズ・ウィスキーの創世期」のページをご参照ください。
3.厚岸(あっけし)蒸留所(北海道厚岸郡)
厚岸蒸留所の稼働は2016年、名前の通り北海道厚岸郡厚岸町にある新しい蒸留所です。
この蒸留所がお手本とするのはアイラ島のスコッチで、アイラ島と似通った環境の厚岸町をその地に選びました。
さらに厚岸蒸留所では現地の原料にこだわっていて、アイラモルト同様ピート(泥炭)※も地元のものを使いたいがために厚岸に蒸留所を作ったと言われています。
2016年10月に蒸留を始めたばかりで、まだ原酒はニューポットやニュボーン※が中心です。
これから5年、10年がたったとき、日本独自のスモーキーなモルトがどのような形でお目見えするのか、楽しみが尽きません。
※「ピート(泥炭)」「ニューポット」「ニューボーン」については、「スコッチ」のページをご参照ください。
4.安積(あさか)蒸留所(福島県郡山市)
1980年代、地ウィスキーブームの際には「北のチェリー、東の東亜、西のマルス」と呼ばれて人気を博した「笹の川酒造」のチェリーウィスキー。
ウィスキー人気の低迷とともに休業を余儀なくされていた同社が、復活を賭けて再生させたのが「安積(あさか)蒸留所」です。
2016年の再稼働となりますので、まだラインナップは多くはありませんが、「山桜」などの存在感のあるウィスキーを世に出しています。
古豪の復活が期待される蒸留所です。
5.額田(ぬかだ)蒸留所(茨城県那珂市)
江戸時代創業の日本酒の蔵元、「木内酒造」が手がけるウィスキー蒸留所が「額田ぬかだ)蒸留所」です。
(ちょっと失礼な言い方ですが)木内酒造と聞いて、日本酒やウィスキーを思い浮かべる人よりも、「常陸野ネストビール」の酒造元としてのほうが有名かもしれません。
1990年後半にブームに湧いた地ビールですが、その後淘汰が進み、いまでは当時の半分以下の醸造者しか残っていません。
そんな中で、今でも国内外で人気があるのが「常陸野ネストビール」ですが、その木内酒造がウィスキー造りに取り組んだのが2016年でした。
木内酒造では茨城県産の大麦麦芽を使用することにこだわっていて、額田蒸留所での県産麦芽使用率は4割、2019年末から稼働した「八郷蒸留所」(茨城県石岡市)では全て茨城県産の大麦麦芽を使用しています。
また、額田蒸留所では効率の良い「ハイブリッド型蒸留機」を、八郷蒸留所では「単式ポットスチル」を導入しています。
革新と伝統が入り交じった、新しい「ジャパニーズ・ウィスキー」造りへの意欲が感じられて頼もしいですね。
6.ガイアフロー静岡蒸留所(静岡県静岡市)
ガイアフロー静岡蒸留所は、精密会社の製造加工を行なっている代表者が、ウィスキー好きが高じて設立した蒸留所で、蒸留開始は2016年10月です。
この蒸留所の特徴は、今ではマニア垂涎のコレクターアイテムとなっている「軽井沢蒸留所」のポットスチルやモルトミル※を使用しているところです。
また、蒸留所の周囲の豊かな杉やヒノキの森を最大限に活用して、自然と一体化したウィスキー造りに取り組んでいます。
具体的には発酵槽に静岡県産の杉を使用していて、さらに蒸留の際に使う燃料にも静岡県産の薪を使うという徹底ぶりです。
ニッカの余市蒸留所など、石炭の直火で蒸留を行なう蒸留所はわずかに存在しますが、薪を使った蒸留というのは世界でも極めて珍しいケースです。
しかしながら「地産地消」という観点で見れば、ジャパニーズ・ウィスキーという範疇にとどまらず、「静岡ウィスキー」フランドが誕生する可能性も秘めています。
2016年10月蒸留開始ですのでまだまだこれからの蒸留所ですが、大いに期待が持てますね。
※「モルトミル」の詳細については、「スコッチ」のページをご参照ください。
7.三郎丸蒸留所(富山県砺波市)
三郎丸蒸留所を運営する若鶴酒造は、1862年創業の日本酒の蔵元です。その若鶴酒造がウィスキーの製造免許を取得したのが1952年、第一次ウィスキーブームの年代と重なりますので、地ウィスキー蒸留所としての歴史は古いと言えます。
また北陸唯一のウィスキー蒸留所としても貴重な存在ですが、大火災や施設の老朽化などにより、近年ウィスキー造りを断念する直前にまで追い込まれました。
これを回避するべく「クラウドファンディング」により資金を集め、地元の支援もあって設備を一新、新しい三郎丸蒸留所として復活を遂げています。
三郎丸蒸留所の特徴は、なんと言っても「ポットスチル」にあります。通常のポットスチルは銅板を叩いたり曲げたりして整形する「板金加工」ですが、三郎丸蒸留所のポットスチルは「鋳造」により作られています。
「鋳造」とは、溶かした金属を砂などの型に流し込み、冷やした後に固まった金属を取り出して整形する加工技術です。
これは当時世界初の試みであり、国内の銅器生産の90%以上を占める富山県に拠点を置く三郎丸蒸留所ならではの発想だと言えます。
ポットスチルはその大きさや形状によっても大きくウィスキーの味わいを左右すると言われています。
鋳造ポットスチルの蒸留で作られた三郎丸ウィスキー、どんな味がするのかとても楽しみですね。
7.長濱蒸留所(滋賀県長浜市)
長濱蒸留所の母体は1996年設立のクラフトビール醸造所で、当時の細川内閣の規制緩和施策を受けて長浜市の町おこしも兼ねて誕生しました。
ビール造りとウィスキー造りは原材料や設備など共通している点が多かったこともあり、2016年年末から本格的にウィスキー造りに着手しました。
日本でも最小クラスの1000リットルのポットスチルから生み出されるウィスキーは、まさに「手作りウィスキー」と呼ぶに相応しく、「AMAHAGAN」という銘柄で販売されています。
ちなみに「AMAHAGAN」とは「長濱」を逆から読んだものです。
最近では山桜の樽で熟成させたウィスキー、「AMAHAGANワールドモルトEdtion山桜」というウィスキーも世に出ました。
先述したように、日本ではジャパニーズ・ウィスキーに明確な定義はなく、輸入したウィスキーを自社のウィスキーにブレンドしたとしても「ジャパニーズ・ウィスキー」を名乗ることは可能です。
敢えてそれをせず、「このウィスキーはジャパニーズ・ウィスキーではなく、輸入ウィスキーをブレンドしたワールドモルトですよ。」ということを正直に消費者に伝えているんですね。
こうした作り手の誠実な態度は、消費者サイドからすると好感が持てて、同時にジャパニーズ・ウィスキー造りに対するプライドも感じられます。
将来が楽しみなジャパニーズ・ウィスキーです。
8.桜尾蒸留所(広島県廿日市市)
桜尾蒸留所の母体となるのは「中国醸造」で、1918年創業の老舗の会社です。
創業当時からウィスキー造りも手がけていて、1980年代には自社モルトと海外からの輸入ウィスキーのブレンデッドウィスキー「戸河内ウィスキー」を発売します。
しかしながら「ウィスキー冬の時代」に突入すると、大量の在庫を抱えて会社存続の危機に立たされます。
転機となったのはジャパニーズ・ウィスキーブームで、ある海外の商社が「戸河内ウィスキー」の在庫を全て買い取るという事態がおきました。
これを受けて中国醸造では海外輸出に軸足を移す訳ですが、この醸造所のユニークな点は、ウィスキーではなく「ジン」を会社の柱に据えたということです。
ただしジンを会社の顔とするだけでは訴求力が弱く、やはりより強いブランドを目指すためには蒸留所が必須だと言う結論になり、2018年に「桜尾蒸留所」が新設されました。
従って桜尾蒸留所ではウィスキーの蒸留のための「単式ポットスチル」だけではなく、ウィスキーの蒸留にもジンの蒸留にも使える「ハイブリッド型蒸留機」も併設されています。
ウィスキーももちろんですが、桜尾蒸留所のジンも飲んでみたいですね。
9.嘉之助(かのすけ)蒸留所(鹿児島県日置市)
嘉之助蒸留所を手がけるのは、「メローコヅル」で有名な焼酎メーカー「小正醸造株式会社」です。
小正醸造の創業は1883年(明治16年)、鹿児島県にある110以上の焼酎メーカーの中で、押しも押されもせぬ存在である小正醸造が、ウィスキー造りに着手したのは2017年でした。
それまで焼酎を世界に広げていこうと挑み続けてきた小正社長ですが、焼酎はなかなか受け入れられず、今度はウィスキーで再び世界を目指そうとして、祖父の名を冠する「嘉之助蒸留所」を設立しました。
焼酎造りで培ってきた蒸留や発酵といった技術を駆使して、世界標準の「ジャパニーズ・ウィスキー」造りに邁進している蒸留所です。
10.遊佐(ゆざ)蒸留所(山形県飽海郡)
遊佐蒸留所を運営する「株式会社金龍」は、1950年に地元山形の日本酒メーカー9社の出資により設立された、山形県唯一の焼酎メーカーです。
金龍では長年、焼酎に頼らない新規事業の開拓が悲願であり、その柱として選ばれたのがウィスキーでした。
遊佐蒸留所の稼働は2018年で、その特徴は最初から「世界標準」を睨んでウィスキー造りに取り組んでいる点です。
スコッチ同様「3年以上の熟成」を経たモルトしか出荷しない方針で、したがって遊佐蒸留所のニューポットもニューボーンもこの世には存在しないことになります。
いわば「ハイエンドのシングルモルト蒸留所」が遊佐蒸留所の特徴だと言えます。
また、熟成や貯蔵庫にも特徴があり、土の上に樽を置いて積み上げて熟成させる、伝統的な「ダンネージ式」※にこだわっています。
熟成にこだわりを持つ「遊佐蒸留所」なので、まだ一般消費者が口にできる日は先になりそうですが、山形県産のジャパニーズ・ウィスキーが呑める日が待ち遠しいです!
※「ダンネージ式」の詳細については、「ジャパニーズ・ウィスキーができるまで」のページをご参照ください。
11.富士御殿場蒸留所(静岡県御殿場市)
2002年にキリンがオーナーとなった「富士御殿場蒸留所」ですが、標高620m、富士山を望む絶景の場所に建てられています。
サントリーやニッカなどと同様、大手メーカーが経営する蒸留所であるにも関わらず、知名度は2社には及びません。
とは言え知る人ぞ知る蒸留所であることは間違いなく、「富士御殿場シングルモルト」や「富士御殿場シングルグレーン」など、過去には傑作ウィスキーも世に送り出しています。(かつては蒸留所内の直売所で購入可能でした。)
また、富士御殿場蒸留所ではモルトウィスキーとグレーンウィスキーを両方とも生産していることでも知られていて、他の蒸留所ではあまり見られない特徴だと言えます。
小規模生産者である「クラフトウィスキー」とは違って、資金力や設備なども潤沢に備えていて、本気でウィスキー造りに取り組めばサントリー・ニッカなどにも引けを取らないウィスキーを作り出すポテンシャルがあります。
ハイエンドのウィスキー造りの復活が待たれる蒸留所です。
12.江井ヶ嶋(えいがしま)ホワイトオーク蒸留所(兵庫県明石市)
「江井ヶ嶋ホワイトオーク蒸留所」を擁する「江井ヶ嶋酒造」の歴史は340年にも及び、日本酒に始まり焼酎・みりん・梅酒からブランデーまで多種多様な種類のお酒造りに関わる「総合酒造メーカー」です。
ウィスキー造りに取り組み始めたのは1960年代、その後地ウィスキーブームが終焉した後も、一定量のウィスキーを作り続けていました。(ウィスキーの製造免許を取得したのは1919年(大正8年)にまで遡るそうです。)
しかしながらジャパニーズ・ウィスキーのブームを迎えると状況は一変、10年前と比べてウィスキーの生産量は約10倍になり、海外からのウィスキーの注文も殺到する事態になりました。
江井ヶ嶋ホワイトオーク蒸留所の一番の特徴は、日本酒の杜氏※がウィスキー造りのトップも兼任している点です。
こうして作られるウィスキーは、蒸留所のある地名をとって「あかし」のブランドで売り出されています。
比較的容易に入手が可能ですので興味のある方は一度お試しください!
※「杜氏」の詳細については、「日本酒」のページをご参照ください。
13.宮下酒造蒸留所(岡山県岡山市)
「宮下酒造」は日本酒メーカーとして有名で、日本酒以外には焼酎やビール製造なども手がけています。
その宮下酒造さんが創業90周年の記念事業として、2012年にモルト原酒の生産に着手しました。
2015年には3年熟成のウィスキーを初めて造り、今では「岡山」「壽光」などのいくつかのブランドが販売されています。
中でも「シングルモルトウィスキー岡山トリプルカスク」は、2020年のワールド・ウィスキー・アワード(WWA)のシングルモルトノンエイジ部門で最高賞を受賞したことで一気にブレイクしました。
私も試飲させてもらいましたが、卓越したバランスを持つ出色のウィスキーで、16,500円という値段でも納得の1本です。
宮下酒造ではこれから、日本酒・ビール・焼酎にとどまらず、ウィスキーやリキュールやスピリッツ造りにも取り組み、「保活的酒造会社」を目指すと宣言しています。
大都市圏や海外での販路拡大に取り組み始めていて、ウィスキーだけでなく様々なお酒の世界展開、ならびに品質向上が期待される蒸留所です。
上記のように主に蒸留所を持つ生産者をいくつか紹介してきましたが、現在でも新たな蒸留所は続々と誕生しており、まだしばらくは蒸留所建設ラッシュは続きそうです。
一方で、大手のスーパーや酒造所などが輸入ウィスキーをブレンドした上で自社ブランドとして売り出す動きも加速していて、ジャパニーズ・ウィスキーを取りまく混乱状態はまだまだ続きそうです。
宇宙熟成について
近年「宇宙ビジネス」が取り沙汰されていて、民間の宇宙ロケットが発射されたりしていよいよ宇宙旅行も現実味帯びてきた感があります。
ウィスキーの世界でも宇宙を視野に入れた取り組みが始まっていて、「宇宙での熟成」の研究がそれです。
ウィスキーのサンプルを国際宇宙ステーション(ISS)に持ち込み、マイクログラビティ(微小重力環境・ほぼ無重力)下で味わいにどのような変化があるのか、「まろやかさのメカニズム」の解明に取り組むのだそうです。
ジャパニーズ・ウィスキーメーカーではサントリーが「山崎」をサンプルに、スコッチではアードベック社が自社のウィスキーを持ち込み、それぞれ実験を重ねているのだとか。
結果が明らかになり、それがウィスキーの味わいにどのような影響を及ぼすのか、発表が待たれる実験ですね。